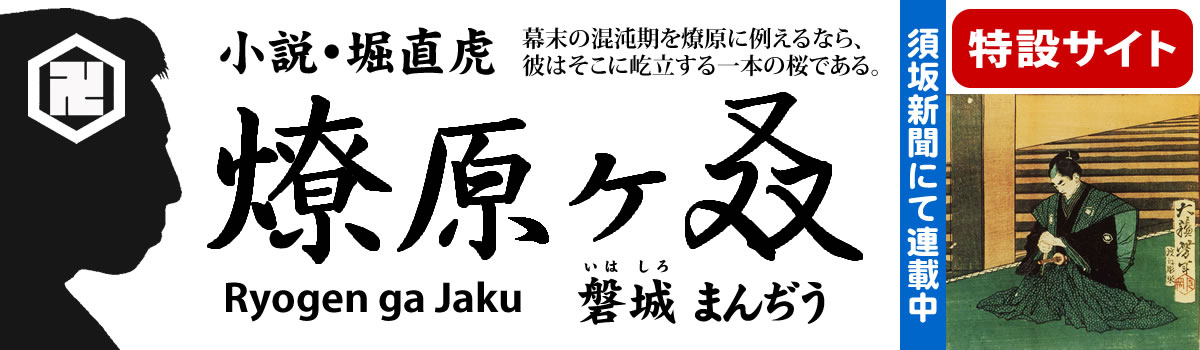
column-11 7両と2分
お糸と生糸の取り引き
2019年12月21日
今回の話の中で、武士は──
「自らは稼がず、全て年貢や税金で生活できてしまう彼らは、金の出入りの調節が全てで、ゼロから価値を生み出し、金銭を獲得する術など生まれた時から持ち合わせていない」
と、筆者は現代の価値観でちょっと意地悪な書き方をしましたが、実際の武士はどうだったのでしょう?
新渡戸稲造の「武士道」からその実像を考えてみたいと思います。

新渡戸稲造
(Wikipediaより転載)
「第10章 武士の教育と訓練」にこうあります。
『武士の教育において守るべき第一の点は品性を建つにあり』とした上で、
『武士道は非経済的である。それは貧困を誇る。(略)「武士の徳たる名誉心は、利益を得て汚名を被(き)るよりむしろ損失を選ぶ」。(略)彼(武士)は金銭そのもの、それを儲けもしくは蓄える術を賤(いや)しんだ。それは彼にとりて真に汚れたる利益であった。』
また、
『“銭を愛する文臣”と“命を愛しむ武臣”を嫌い(「黄金と生命を惜しむことは甚しく賤しめられ)、
「なかんずく金銀の慾を思うべからず、富めるは智に害あり」と。(略)経済のことを口にするは悪趣味であると考えられ、各種貨幣の価値を知らざるは善き教育の記号(しるし)であった。』
──と。
現代の拝金社会に偏り過ぎた感覚からすると非常に考えづらいのですが、幕末は、西洋の日本への進出に伴い、この価値観は根底から覆されていくことになります。
それまでの日本が精神大国と言われてきたのは、武士道におけるこんな背景があったからでしょうが、それにしても今から120年も前に刊行されたにも関わらず、この時すでに“拝金思想”という言葉を使っている新渡戸稲造の先見には驚きです。
明治維新を境に怒涛の如くなだれ込んできた西洋の価値観が、日本古来の全てのものを飲み尽くしてしまったことは、現代の日本の自然の生態系の危機にも似て、まるで外来生物が在来種の生存を脅かしている実情と重なって見えてしまいます。
それがグローバル化の中に置かれた個の、抗えない摂理と言ってしまえばそれまででしょうか。
堀直虎の切腹は、日本人たる精神の最後の灯だったと主張するのがこの小説の大きなテーマです。
お糸の求婚にうろたえる
2020年2月1日
今回は幕末における須坂から見た生糸・蚕種業の流れを記しておきたいと思います。
そもそも絹というものが中国から日本に伝わったのは弥生時代だったと言います。
その後、195年に百済から蚕種が伝わり、更に283年に養蚕と絹織物の技術が伝わったそうです。
奈良時代に入ると養蚕は全国に広まっていき、租庸調の税制に組み込まれるようになりました。
長い間、生糸は輸入に頼っていましたが、京都の西陣を中心としたいわゆる登せ糸の需要が高まると、江戸時代に入り各地でその生産が始まります。
その変遷を須坂の視点を含めた年表にまとめてみました。
享保19年(1734) (須坂)松代領小河原村で養蚕が行われていた。
文化9年(1812) (須坂)藩による桑園拡大奨励。
文化~文政期(1818~30) (須坂)養蚕奨励。(登せ糸)
天保~嘉永年間(1830~1854) (須坂)糸仲間結成。
1850~60年代 ヨーロッパで蚕の微粒子病大流行。フランス養蚕業壊滅的状態。
嘉永6(1853) ペリー来航。
嘉永7年(1854) (須坂)糸師の数37人。
安政6年(1859) 横浜開港。
繭の需要増大、製糸・蚕種業急速に発達、繭価高騰。

万延元年(1860) 五品江戸廻送令。生糸・雑穀・水油・蝋・呉服の貿易統制。横浜直送禁止。
文久2年(1862) 生糸の輸出前年の3倍に成長。蚕紙の輸出禁止(列強諸国の圧力で1年で廃止)。
文久3年(1863) 江戸廻送令、本格施行と取り締まり強化。生糸輸出の減少。生糸価格暴落。
元治元年(1864) 列強諸国に廻送令撤回を強く迫まられ、実質的に放棄される。
元治2年(1865) 2月、徳川家茂フランスへ1500枚の蚕卵紙を寄贈。同年(慶応元年)10月、蚕卵紙1万5000枚寄贈。
慶応元年(1865) 幕府「生糸并蚕種紙改印」制度。蚕紙・生糸の生産者への冥加銀取り立て。生産農家の「世直し一揆」勃発。
(須坂)7月、蚕運上取り調べ役を設置し冥加金を課す。
慶応2年(1866) (須坂)輸出・国内用の生糸売買に免許制をしく。
慶応3年(1867) 6月、フランスより蚕卵紙の返礼としてアラビア馬が寄贈される。
慶応4(1868) (須坂)糸仲間加入者144人に。
明治6年(1873) 「生糸製造取締規則」公布。生糸の出荷に印紙義務。
以後、政府は生糸の増産・輸出政策への関与を強める。
※写真は「神名川横浜新開港図」1960年
あちこちの資料からひっぱってきたので間違っている箇所もあるかも知れませんが、おおまかな流れは掌握できるのはないでしょうか。
徳川幕府と長州藩の攻防
2020年3月7日
文久年間の京都での長州藩の動きがなければ、幕末はまったく違った形になっていたでしょう。
そのとき活躍したのが、筆者が高杉晋作と並んで大好きな久坂玄瑞です。

久坂玄瑞(ウィキペディアより)
小説にはあえて登場させませんでしたが、彼がいなければ日本の歴史は別の道筋をたどったに違いありません。
言わずと知れた吉田松陰の双璧の一人ですが、彼の時代を動かすパワーはいったいどれほど凄かったのか、実際にお会いしてお話ししてみたいです。(笑)
もともとは医者の息子らしいですが、松下村塾に入門してよりその革命児としての頭角をぐいぐい顕したといいます。
松陰の妹を嫁にしたくらいですから、師からの信頼も相当厚かったのでしょう。
当時にして「討幕」という発想は、彼から発信されたと言っても過言ではありません。
坂本龍馬を脱藩させた因も彼にあったとする説もあります。
徳川家光以来229年ぶりとなった将軍上洛から、賀茂・石清水行幸への幕府権威を失墜させようとした長州藩の巧みな画策は、彼以外にいったい誰が思いつくでしょうか?
しかし時代の大きな流れが彼に追い付つくにはまだ少し早かった──。
8月18日の政変により長州藩は失脚し、その後の禁門の変(蛤御門の変)で彼は炎の中で自刃します。
『ホトトギス 血に鳴く声は有明の 月より他に知る人ぞなき』
この辞世では、夜明けの月に志半ばの無念さを託します。
ホトトギスは血を吐いてなお鳴き続けるのだそうです。
吉田松陰から発信された時代変革のほとばしる情熱は久坂玄瑞へ、そして久坂玄瑞から高杉晋作へとバトンが託されたのでした──と筆者は考えています。
徳川家茂と孝明天皇
2020年4月4日

孝明天皇(Wikipediaより転載)
孝明天皇といえば幕末の激動期を生きた天皇です。
この小説の当時は32歳、妹の和宮は騒然とした世の中を鎮めるために時の将軍徳川家茂に嫁ぎました。
もともとこの天皇は攘夷思想を持っていたので、開国を志向する徳川幕府とは水と油の関係ですから、尊王攘夷の長州藩とは非常に結びつきやすかったというわけです。
文久年間の京都は、そんな攘夷か開国かで激しく争うあの手この手のかけひきの連続。
ところが長州藩はあまりに過激すぎた(笑)
やがて京都を追放されてしまいます。
世情のゴタゴタを反映するように、徳川家茂と天皇の関係もそうだったかといえば、これはまた別の話で、家茂と和宮の関係を見るかぎり、後世に語り伝えられるほどの仲睦まじさだったと言われますから、きっと天皇に対しても同様の接し方をしたでしょう。
筆者はここに徳川家茂の優れた人物性を感じるのです。
このとき家茂若干17歳。
倍近くも離れた義理の兄に対する態度は、きっと礼節正しい奥ゆかしいものだったに違いありません。
この二人は、幕末が語られる上ではどちらかといえば脇役的な存在として扱われがちですが、特に徳川家茂という人物に興味をそそられる筆者です。
俊姫、江戸から信州上田へ
2020年5月2日
さて今回は、上田藩の俊姫様が、引っ越しの手伝いの男たちに振る舞おうとした『松の寿司』のお話をしましょう。
『松ヶ鮨』、あるいは、深川の安宅(あたけ)六間堀(現在の新大橋付近)にあったことから『あたけ 松のすし』とも言われたこの寿司は、江戸前寿司職人である堺屋松五郎が考案した超贅沢な高級お寿司だったと言われています。
六軒堀には御船蔵があり、安宅丸という大船が置かれていたそうで、六軒堀は別名安宅河岸(あたけがし)とも呼ばれていたそうです。
今では寿司といえば回転寿司を思い浮かべる人も多いでしょうが、そもそも握りずしが誕生したのは文政年間(1818~1830)頃と言われています。

縞揃女弁慶 安宅の松(一勇斎国芳)
引用:東京都立図書館
https://www.library.metro.tokyo.jp/
それまでの寿司といえば、保存をきかすのために自然発酵させた押し鮨でしたが、品川沖(江戸湾)で捕れる新鮮な魚貝類(いわゆる江戸前)を、握った酢飯の上に乗せて食べるいわゆる“握り寿司”を考案した人は華屋与兵衛だとされています。(堺屋松五郎という説も)
その寿司は発酵させる手間がなく、せっかちな江戸っ子にとってはおあつらえ向きだったのでしょう。
庶民受けする与兵衛の握り寿司は大ヒットすることになります。
それを見ていた商売敵の堺屋松五郎。
知恵をしぼって、逆に高級なネタばかりを使ったバカっ高い寿司を売り出して対抗します。
客はどんどん松五郎の方へと流れていきました。
与兵衛も黙ってはいません。
あの手この手の旨い寿司を考案して客を取り戻します。
すると負けじと松五郎、寿司にご祝儀を付けて売り出せば、評判は江戸の噂となって人気沸騰。
いわばこうしたライバル同士の競い合いが、寿司の食文化の発展を促したとも言えますね。
この話は以前、NHKの『歴史秘話ヒトリア』でも取り上げられていて、筆者も興味深く視聴したのを覚えています。
そんな『松の寿司』の人気を裏付ける歌川国芳(一勇斎国芳)の浮世絵があります。
タイトルは『縞揃女弁慶(しまぞろえおんなべんけい)』──。
これは同タイトルのシリーズのうちの一枚で、左手に持つ折箱には『あたけ 松の寿之」とありますから『松の寿司』に違いありません。
弁慶というのは着物の柄のことで、九郎義経の家来の方ではありません(笑)
女性は、右下の小さな子どもの母親でしょうか?
絵の上部には梅屋という人が詠んだ狂歌が書かれており、そこには
『をさな子も ねだる安宅の松の鮓(すし) あふぎ(扇)づけなる袖にすがりて』
とあります。
幼い子どもは扇の柄の着物を掴み、
「早く食べさせておくれ!」
とねだります。
そして女性の右手の皿の上には、二つの玉子巻き寿司の上に海老の握りずしが乗せられており、下にはサバの押し鮨もあるようで、
「ちょっとお待ちよ!高いんだから」
と、折箱を隠すようにして、ふさがった両手を動かせずに手をこまぬいています。
「此松のすしは握りすしの初めなるも、昔時押すしの形を存せんとの意か、一人前の盛り皿の中に、必ず押すしを交せり(『江戸名物詩』)」
この文面から、松の寿司のそれは、握り寿司の他に押し鮨も一緒に提供していたようですね。
時を越えても美味しいものは美味しいに決っています。
江戸で一番贅沢な寿司と言われた『松の寿司』の味をしめたこの子は、いったいどんなグルメに成長するのでしょうかねぇ?(笑)